- ホーム
- ニュース
- ~文部科学省 「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト」~ ドローン(UAV:無人航空機)を活用し、鹿児島県・桜島で高層気象観測 日本気象協会と京都大学防災研究所が共同調査 火山周辺における地上1000mまでの風向や風速、気温などを計測
ニュース
~文部科学省 「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト」~ ドローン(UAV:無人航空機)を活用し、鹿児島県・桜島で高層気象観測 日本気象協会と京都大学防災研究所が共同調査 火山周辺における地上1000mまでの風向や風速、気温などを計測
2017.04.19
プレスリリース
一般財団法人 日本気象協会(本社:東京都豊島区、会長:石川 裕己、以下「日本気象協会」)は、文部科学省選定事業「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト」の一環として、京都大学防災研究所(附属 火山活動研究センター長:井口正人教授)と共同で、4月18日(火)~4月20日(木)、鹿児島県鹿児島市桜島にて、ドローン(UAV:Unmanned Aerial Vehicle、無人航空機)を活用した高層気象観測を実施します。
今回の観測は、火山災害の軽減に資する火山研究の推進を目的とした「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト」で掲げる課題テーマ「火山災害対策技術の開発」のうち、「リアルタイムの火山灰ハザード評価手法の開発」を目指す取り組みとして実施しています。複合気象センサーを搭載したドローン(UAV)を活用し、桜島(計3地点)の高層気象観測を行うことで、火山周辺の風の場(地上から上空までの風の吹き方)を把握するとともに、複雑な地形が天気に与える影響(気象場)の評価や、火山灰の降灰予測に資するデータの取得を目的に、以下の通り調査を行いました。
【調査内容】
① 複合気象センサーを搭載したドローン(UAV)を複数の高度で空中停止させ、高度1000mまでの風向・風速・気温・湿度の鉛直プロファイル(注1)を計測
② ドップラーライダー(注2)で風向・風速の鉛直プロファイルを計測し、ドローン(UAV)の鉛直プロファイルと比較検討
 |
|
ドローンに複合気象センサーを搭載し、 |
【調査地点】
調査地点は桜島の京都大学防災研究所 ハルタ山観測室(A地点)、黒神地区 (B地点)および有村地区(C地点)
 |
| 観測地点は、京都大学防災研究所ハルタ山観測室 (A地点)、黒神地区(B地点)、有村地区(C地点) の3カ所 |
【調査で使用した機器】
| ドローン(UAV) : | ルーチェサーチ製「SPIDER CS-6」 |
| 機体重量…3,800g | |
| 外形寸法…950×950×400mm | |
| 駆動…モータ駆動 | |
| 耐風速…15m/s以下 | |
| 飛行時間…10分~25分(リチウムポリマー電池) | |
| 搭載重量…4,000g |
| 風向風速計 : | セネコム製「超小型超音波風向風速計 SE-702」 |
| 重量…250g | |
| 外形寸法…50mmΦ×70mm | |
| 風速…0-50m/s | |
| 分解能…0.1m/s |
| ドップラーライダー: | 三菱電機社製 「小型光ファイバドップラーライダシステム」 |
観測初日の4月18日には、鹿児島の報道関係者を対象としたドローン(UAV)を活用した高層気象観測の見学会を開き、気象センサーを搭載したドローンが高度を変えながら飛行する様子などを公開しました。
 |
 |
|
超小型超音波風向風速計を搭載したドローン |
桜島周辺の高層気象観測のために飛行するドローン |
観測前に、今回の調査について報道関係者向けガイダンスを行った京都大学防災研究所附属火山活動研究センター長の井口正人教授は、「火山灰の拡散問題を解決するには、山の近くの風、風向風速がどうなっているかを知らなければならない。そのためには実地の観測が必要。目指しているところは『明日の火山灰予報』です。」と、今回の調査の意義と未来像について説明しました。
| 京都大学防災研究所(附属 火山活動研究センター長)井口 正人 教授 1958 年 岡山県生まれ 1981 年 京都大学理学部卒業 1994 年 「桜島の火道内で発生する火山性地震の鉛直膨張モデル」で京都大学博士(理学)の学位を授与される 1995 年 京都大学助教授に昇任 2012 年 京都大学教授に昇任 |
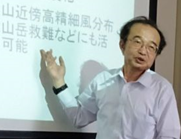
4月18日の見学会で報道関係者に |
今回の観測・調査を通して、ドローン(UAV)を用いた気象観測によって、より正確な鉛直方向の気象状況取得が可能であることが実証されれば、人の立ち入りが困難な場所での高精度な観測が可能となります。
また観測を通じ、将来的には噴火時の降灰リスクなどに関する精度の高い予測シミュレーションモデルの開発へつなげることができます。今後、日本気象協会と京都大学防災研究所は共同で、予測シミュレーションモデルの情報を元に、いち早く地域住民の避難行動に結びつけるための情報提供の可能性を検討していきます。
(注1)鉛直プロファイル 高さごとの測定値
(注2)ドップラーライダー 上空に向けて発射したレーザー光の反射波を捉え、上空の風を測定する装置
【 別添 】
■ 文部科学省選定事業「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト」について
「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト」は、平成26年(2014年)9月に発生した御嶽山(長野県・岐阜県)の噴火等を踏まえ、火山災害の軽減に資する火山研究の推進、広く社会で活躍する火山研究人材の裾野を拡大するとともに、火山に関する広範な知識と高度な技能を有する火山研究者となる素養のある人材を育成することを目的として、文部科学省が平成28年度(2016年度)に立ち上げた事業です。今後10年間で、日本の火山の観測・予測・対策体制の改革を目指しています。
今回のドローン(UAV)を活用した高層気象観測は、「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト」の課題の1つである「火山災害対策技術の開発」のうち、リアルタイムな降灰予測などを可能にする「リアルタイムの火山灰ハザード評価手法の開発」にあたって行われました。
[URL] 文部科学省選定事業「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト」 http://www.kazan-pj.jp/
■ 京都大学防災研究所(附属 火山活動研究センター)について
京都大学防災研究所は1951年の創設以来、わが国や諸外国を襲ったさまざまな自然災害に対峙しつつ、「災害学理の追求と防災に関する総合的・実践的な研究の推進」をミッションとした研究と教育を展開。災害を起こす事象の予測と究明、災害を予防するための技術開発、災害に対する危機管理、災害後の対応や復旧等、災害の軽減に資する研究に総合的に取り組んでいます。研究所の本拠を京都大学宇治キャンパスに構えるとともに、全国各地に計15の実験所・観測所を保有し、フィールド調査・観測・大型実験等に根ざしたユニークな研究と教育に励んでいます。
京都大学防災研究所の附属施設のうち、火山活動研究センターは、わが国で最も活動的な火山である桜島を全国的なレベルでの野外観測拠点として、学際的な実験・観測を総合的に推進しています。桜島や薩摩硫黄島、口永良部島、諏訪之瀬島など霧島火山帯に属する火山群をフィールドラボラトリーと位置づけ、常時観測と現地観測調査を行っています。さらに、防災研究所の共同利用・共同研究拠点など多様な枠組みで、国内外の大学および研究機関と共同観測・研究を実施しています。また、国・地方自治体と連携して火山災害の軽減に努めています。
[URL] 京都大学防災研究所 https://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/
京都大学防災研究所附属火山活動研究センター http://www.aso.vgs.kyoto-u.ac.jp/menu/index.html
■ 一般財団法人 日本気象協会について
1950年に誕生した日本気象協会は、天気予報に代表される気象予測事業に加え、再生可能エネルギー、環境アセスメント、大気解析事業、防災・減災・安全管理に関する事業など、気象に関するコンサルティング事業を通じ、公共に資する企業活動を展開しています。
[URL] 日本気象協会 https://www.jwa.or.jp/
以上
PDFダウンロード:【日本気象協会報道発表】ドローンによる桜島観測レポート_
